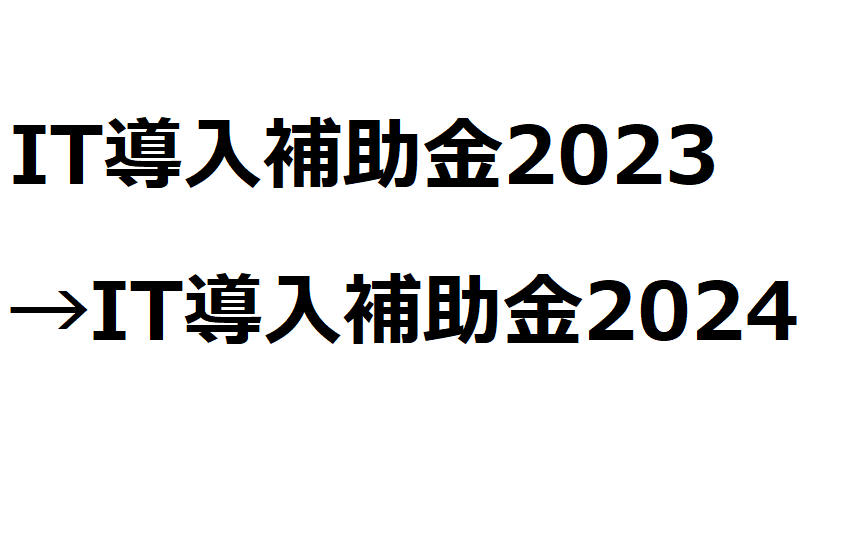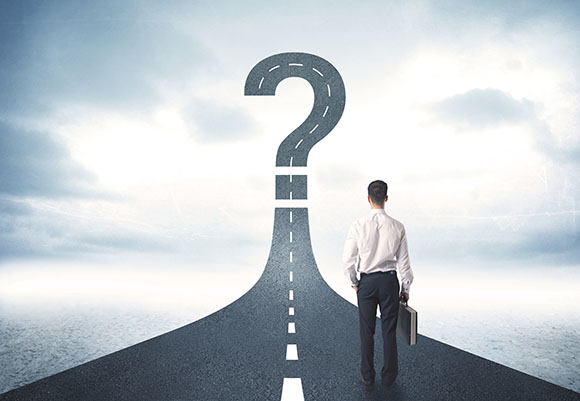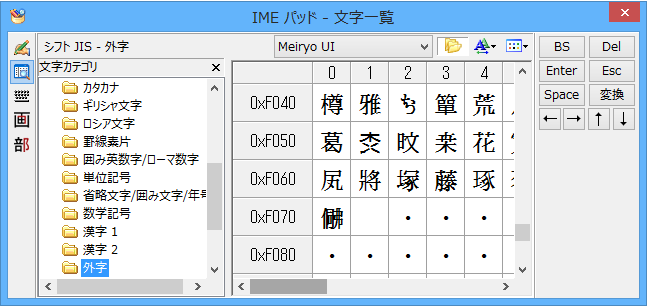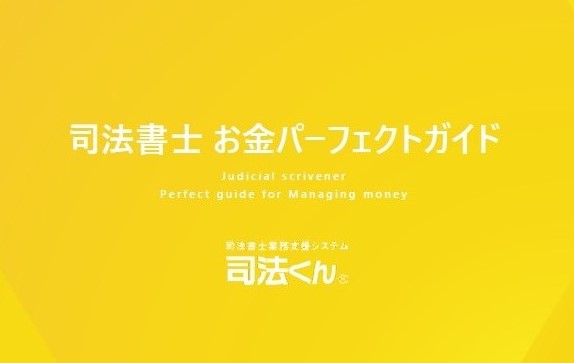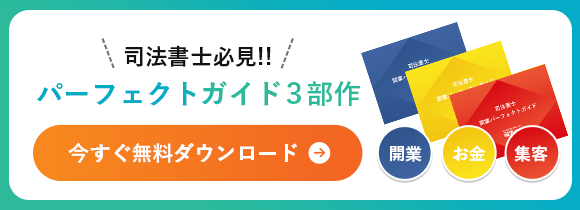司法書士事務所を開業する際、場所の選択は特に重要です。司法書士事務所の経営環境は、都市部と地方で大きな違いがあります。今回は、都市部開業と地方開業、それぞれのメリット・デメリットや注意点をご紹介します。また、開業場所を選ぶときにもう一つ考えるべきことは、事務所の立地や事務所のタイプです。どのような場所に事務所を構えるとお客様に来てもらえるのか、事務所のタイプの特徴をご紹介します。
1 司法書士を開業する場所―都市部と地方を比較

1 司法書士は偏在している
司法書士の人数は、23,059人(2023年4月1日時点、日本司法書士会連合会調べ)。2012年の20,670人からおよそ10年間で3,000人ほど増え、近年の傾向を眺めると、毎年900人程度の新規登録があり、600人程度が登録を取り消しているため、おおよそ毎年300人程度増加していることが分かります。司法書士の増加は東京など都市部で顕著であり、地方にはむしろ減少している地域もあります。2021年の司法書士の人数は1位の東京都が4,395人、2位の大阪府が2,433人ですが、少ない県の鳥取県では92人、島根県では107人です。
司法書士の人数がこのように偏在している理由は、基本的には仕事そのものが偏在しているように見えるためです。司法書士の仕事の多くは、土地や建物の不動産登記や、会社や各種法人の商業・法人登記です。このような仕事は経済活動が活発な都市部に集中しているため、必然的に司法書士も都市部に偏在しやすい、という結果になっています。
・仕事があるか―案件と競争
これまでの解説ですと、案件が多い都市部で司法書士事務所を開業するのが良いように思えてきますが、そうではありません。開業を考えるうえで重要になるのは司法書士1人当たりの案件数です。司法書士1人当たりの土地・建物の登記件数は全国平均で約385件ですが、これを法務局管内別にみると東京管区より仙台管区(東北)や札幌管区(北海道)が多くなります。商業登記の全国平均は約57件で、地域別でみると東京管区が突出していますが、他はそれほど大きな違いはありません。司法書士1人当たりの人口の全国平均は約5,700人、認定司法書士1人当たりは約7,700人ですがこの数字は東京ブロックよりも東北ブロックや北海道ブロックが上回ります。開業後に取れる案件を考えると、都市部は必ずしも有利とはいえません。
・都市部では大規模司法書士法人が台頭
都市部で開業する問題点は他にもあります。2003年に司法書士事務所の法人化が認められて以来、大規模な司法書士法人が増えてきました。大規模司法書士事務所の多くは都市部に集中しています。業務の合理化により案件数を稼ぎ、価格競争で勝利するビジネスモデルは「登記工場」とも呼ばれています
2 都市部で開業する場合の戦略と注意点
都市部で開業する場合、多数の競争相手の中に埋没しない事業戦略、すなわち差別化が必要です。薄利多売では大規模司法書士事務所に勝てないので、登記を中心とした価格競争では生き残れません。開業する地域の特性を見極めたうえで、その地域に適した分野に集中して、地域の中でトップになる必要があるでしょう。
3 地方で開業する場合の戦略と注意点
地方では都市部と比べて競争は少ないですが、できるだけ守備範囲を広げて取りこぼしを減らす「くらしの法律家」戦略を取る必要があります。地方では濃密な人間関係のなかで仕事を回す習慣が強いので、地域活動に参加することなどによって人脈を広げれば、徐々に仕事を紹介してもらえるようになるでしょう。地域によっては日本司法書士会連合会が実施している「司法過疎地開業支援事業」による開業・定着のための支援を受けることができます。
2 司法書士を開業する立地―立地を考えるときのポイント

都市部で開業するにせよ、地方で開業するにせよ、事務所を構えるときには場所柄も重要です。司法書士事務所を開業するのに適した立地を考えるときのポイントをご紹介します。
1 訪問型か来客型か?
インターネットを使えば日本全国から集客できますが、開業後に実際に仕事を依頼してくれる顧客は、事務所近くの会社その他の法人や個人がほとんどです。そうした人々はなんらかの交通機関を使って事務所を訪れます。司法書士が自らお客様を訪問する営業スタイルもあります。移動にかかる時間やコストは誰にとっても見過ごせません。事務所に来てもらうのであれば来やすさが、訪問するのであれば行きやすさが重要です。
また、事務所の住所などの情報をGoogleなどの無料サービスに登録すると、検索で表示されやすくなり、地図サービスで見つけてもらいやすくなります。
以前は、司法書士事務所と言えば、登記所や裁判所の周辺に集中していましたが、現在は登記の申請などをオンライン上でできるようになっているので、今日ではその必要性は薄れています。顧客の来やすさや自分の行きやすさを優先して立地を考えましょう。
2 都市部で開業するときの立地条件
都市部では、電車やバスなどの公共交通機関が発達しています。駅から徒歩10分以内で道順が分かりやすい場所であれば、アクセスを調べた段階で「遠い」と敬遠されることはないでしょう。
3 地方で開業するときの立地条件
車で移動することが多い地方であれば、考えておくべきは道路事情です。駐車場が利用しやすいことも考慮に入れる必要があります。
3 司法書士を開業するときのオフィスのタイプ―自宅?賃貸オフィス?他には?

司法書士を開業する地域が決まったら、その地域で利用できるオフィス物件を探すことになります。自宅開業や、オフィスを借りての開業をはじめ、その他にもさまざまな選択肢があります。オフィスのタイプごとにその特徴をご紹介します。
1 自宅開業
自宅で開業すれば、開業費用を最低限に抑えることができます。自宅を改築する場合は、改築規模によって費用に開きが出ます。訪問型の営業で自宅開業するのであれば改築は不要であり、最低限の事務機器の購入や手続き費用だけで開業することができます。
2 SOHOマンション
SOHOとはSmall Office/Home Officeの略であり、マンションを事務所として利用することを意味します。SOHOマンションとして提供される物件は築浅のものが多く、きれいでイメージも良いため、集客しやすいという利点があります。SOHOマンションはそこまで広くないことが多いため、開業初期に使用するというのも一つの選択肢です。
3 レンタルオフィス
レンタルオフィスとは、業務に必要な机やイス、事務機器などを備えたオフィスを借りるタイプです。備品をそろえる必要がないことや、短期間契約で借りることができるという点で開業に適しています。シェアオフィスのようにオフィスを共同で利用し、机や一部のスペースを占有する形態も存在します。
4 オフィスマンション
オフィスマンションは、マンションの一室を事務所専用として借りる形態です。開業として思い浮かびやすいのはこのタイプでしょう。礼金・敷金なども含めて一定の費用がかかります。都市部なら公共交通機関のアクセスの良さ、地方なら車でのアクセス、駐車場の確保や近隣のパーキングスペースなど確認しておきましょう。
5 テナント
テナントは、市街地の大きなビルを区画に区切り、オフィスや公共施設を入居させることで利便性を高めたビルに入居する形態です。利用しやすい場所にあることや、施設が集まっていることで高い集客効果を期待できますが、費用もかなり高額となります。
4 まとめ
以上、司法書士を開業する際の場所選びについて解説しました。最近では、競争を避け、地元でゆとりのある生活をするために地方での開業を選択する方も多いようです。開業した後にどのような仕事がどれだけ回ってくるのかを、ある程度シミュレーションしてから開業することをおすすめします。