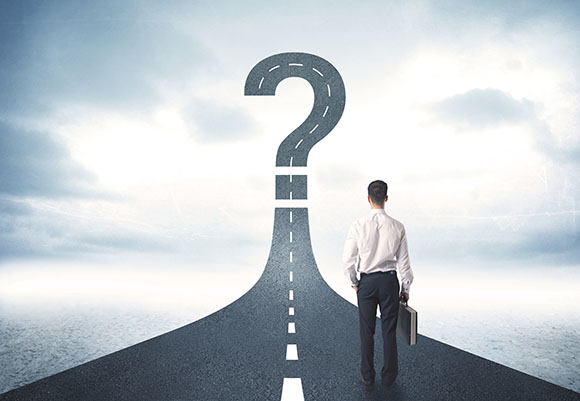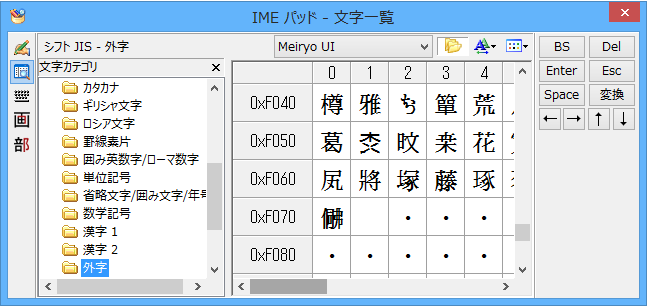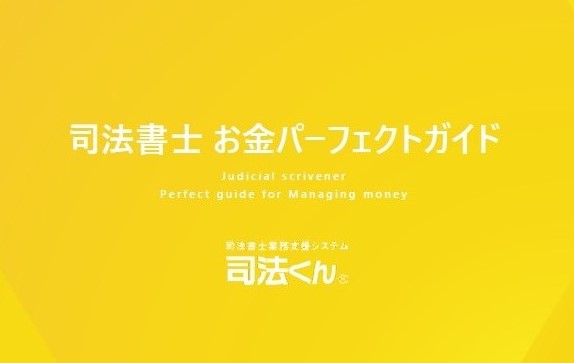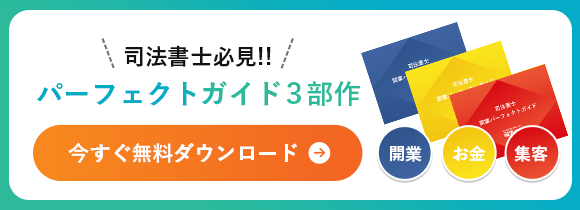1 司法書士試験に合格した後の進路
 まず、司法書士試験に合格した後にたどる進路についておさらいしてみましょう。司法書士として一般企業の法務部に就職したり、司法書士事務所に就職したりと様々な場合がありますが、実際にその中でどのような業務をするか、どのようなスキルを身につけられるのか、ケースごとに確認してみましょう。
まず、司法書士試験に合格した後にたどる進路についておさらいしてみましょう。司法書士として一般企業の法務部に就職したり、司法書士事務所に就職したりと様々な場合がありますが、実際にその中でどのような業務をするか、どのようなスキルを身につけられるのか、ケースごとに確認してみましょう。
1 一般企業に就職する
企業では法務や総務として雇用される場合が一般的です。商標登記や株主総会、社内コンプライアンスに関わる広報業務、各種公的書類の作成など、業務内容は多岐にわたります。特に商品・不動産に関わる登記の知識などは専門性が高く、司法書士の能力が存分に活きるでしょう。また、近年は「企業のコンプライアンス遵守」も社会的に重要視されているため、司法書士のニーズも高いといえます。 書類作成や各種手続きなどをはじめとして、多岐にわたる業務をこなすため、幅広い知識や経験を積めるメリットがある一方、多忙になりがちというデメリットもあります。企業の観点から、幅広い経験を積みたい方にはおすすめの進路といえるでしょう。2 司法書士の資格を活かして就職する
次に、司法書士の資格を活かして、実際に司法書士事務所や法人に従事する場合についてご紹介します。司法書士事務所・合同事務所では実際にどのような業務をするのかチェックしてみましょう。 ①司法書士事務所に就職する 司法書士試験の後、司法書士事務所に就職するケースです。司法書士試験の合格後の進路としてはごく一般的なケースで、不動産や銀行に関わる登記業務や相続・贈与に関わる近隣トラブルの相談などが主な業務です。その他に、公正証書の作成や相談の打ち合わせ、役場での書類収集や商工会への出席などを行う場合もあります。 司法書士事務所で働くメリットとしては、司法書士としてこなす業務フローを一通り経験できるほか、事務所経営のノウハウや人脈を得やすい環境で働けることなどが挙げられます。「将来的に独立を考えているものの、いきなりの独立は少し不安」という方は、司法書士事務所に就職して様々な業務に携わり、経験を積むのも一つの方法でしょう。 ②司法書士法人や合同事務所に就職する 最後に、司法書士法人や合同事務所に就職するケースについて解説します。司法書士法人は、司法書士事務所と違って大規模な案件に携われたり、組織として体系化されていたりするという特徴があります。また、司法書士法人では社会保険の加入が義務付けられているため、福利厚生面は司法書士法人の方が優れている可能性があります。 とはいえ、司法書士の法人制が規定されてからまだ十数年しか経過しておらず、実際には組織として体系化されていない司法書士法人も少なくありません。司法書士法人や合同事務所へ進むことを考えている方は、口コミや体験就労などを経て、内情を確認してから決めるのがいいでしょう。3 試験合格後すぐに独立する
さて、ここまで司法書士試験に合格した後の就職先についてみてきました。ここからは、司法書士の試験合格後に開業したり事務所を設立したりする、独立ケースについて解説します。 ① 個人事業主として司法書士事務所を開業する 個人事業主として司法書士事務所を開業する場合、いくつか抑えておくべきポイントがあります。具体的には、 ・事業計画の策定 ・開業資金の工面 ・事業理念の確立 ・開業にともなう設備の準備 ・集客方法の予測と決定 ・司法書士ソフトの選定 上記のような点がポイントです。 まず、事業計画の策定についてですが、開業する理由や事業内容、事業の将来性・成長性について、中長期のスパンで事業計画書に落とし込んでみましょう。開業資金の工面に際して、銀行などから融資を受けるときには、試算表や事業計画書の提出を求められるケースもあります。しっかりと作り込むようにしましょう。 お金を貯めて自己資金で開業する場合でも、あらかじめ計画を練っておくことは非常に重要です。融資の有無に関わらず、まずは事業計画を立てることをおすすめします。 事業計画を作りこむ際は、事務所のカラーや軸がブレないように事業理念を明確にすること、事業計画の中に、デスクや事務用品、ネット回線など、オフィス環境や設備について盛り込むことを忘れないようにしましょう。 司法書士として独立開業する場合に一番のネックとなるのが、集客や顧客の獲得ともいわれています。そのため、あらかじめ集客の方法を練っておくことも大切です。具体的には、セミナーや無料相談会の実施、ホームページなどによるWeb集客といった方法があります。開業後に顧客が集まらずに廃業せざるを得ない、ということがないように、開業前に集客のノウハウについても調べておきましょう。 さらに、開業後の司法書士業務を円滑に進めるためにも、司法書士ソフトの利用は欠かせません。様々な業務支援ソフトがあるため、導入実績やコストパフォーマンス、サポート体制などを比較して選んでみてください。 ② 司法書士事務所や合同事務所を設立する 法人として司法書士事務所や合同事務所を設立する場合、先にご紹介した個人開業でのポイントに加え、登記が必要になったり、出資金の払い込みなどが必要になったりします。株式会社の設立と異なり、公証人役場での認証などは不要なので、株式会社の設立に比べると開業は容易といえるでしょう。 また、法人の場合はかかってくる税金も変わります。個人事業主では、所得税・住民税・消費税・個人事業税がかかるのに対して、法人の場合には法人税・法人事業税・法人住民税・地方法人特別税・消費税・固定資産税などが発生します。単純に比較すると、個人事業主には4つの税が、法人の場合は6つの税が発生することになりますが、事業の収益によってどちらが得になるのかは変わります。個人開業をした後に、収益が安定化してきた段階で法人化の手続きをとることもできるので、税金面に関してもあらかじめ考慮した上で選択するのがいいでしょう。2 司法書士は転職しやすい資格
 司法書士は資格の専門性の高さに加え、司法書士事務所・一般企業の総務・法務・企業内司法書士など、転職先の候補が多く、転職しやすい資格であるといえます。また、司法書士専門の転職サイトなどもあるため、求人に困ることも比較的少ない業種です。さらに、司法書士には定年がないというのも魅力の一つです。未経験や新卒・第二新卒・40代・50代などの垣根なく、仕事を続けることができます。
司法書士は資格の専門性の高さに加え、司法書士事務所・一般企業の総務・法務・企業内司法書士など、転職先の候補が多く、転職しやすい資格であるといえます。また、司法書士専門の転職サイトなどもあるため、求人に困ることも比較的少ない業種です。さらに、司法書士には定年がないというのも魅力の一つです。未経験や新卒・第二新卒・40代・50代などの垣根なく、仕事を続けることができます。
3 司法書士が即独に成功する秘訣
 ここからは、司法書士が即独に成功する秘訣をご紹介します。「未経験からすぐに独立はできるものなの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、結論からいうと、未経験でも、すぐに独立することができます。これから紹介する3つのポイントを抑えて、独立の際の参考にしてみてください。
ここからは、司法書士が即独に成功する秘訣をご紹介します。「未経験からすぐに独立はできるものなの?」と不安に思う方もいるかもしれませんが、結論からいうと、未経験でも、すぐに独立することができます。これから紹介する3つのポイントを抑えて、独立の際の参考にしてみてください。
1 即独に成功するマインド
司法書士に限らず、どの業界でも未経験からの独立開業には分からないことが沢山発生します。そのため、分からないことがある場合は経験者にアドバイスを求めたり、イベントに参加してその道の先輩に話を聞いたりと、謙虚で勤勉なマインドを心がけるようにしましょう。2 即独とお金
即独する場合にはお金の問題も密接に関わってきます。司法書士試験の勉強代や研修費用など、受験費が影響して開業資金が工面できないケースもあるでしょう。試験合格からすぐに独立を考えている場合は、事前に資金を用意しておいたり、金融機関から融資を受けるために計画を立てたりしておきましょう。3 即独と人間関係
独立にあたって、各種イベントへの参加や案件獲得のために、人間関係・人脈は重要な要素です。すでに持っている人脈はもちろん、イベントなどに積極的に参加したり、Webを通じて人間関係を広めたりする努力が必要です。開業してから何かトラブルがあった際に相談するためにも、幅広い人間関係を構築しておくと安心です。その中でもとても大事な関係が司法書士同士のつながり。業務でわからないことも聞ける司法書士がいるととても安心です。4 司法書士の即独の事例研究(司法くんの導入事例から)
 ここからは、司法書士の即独事例についてご紹介します。共通しているのは司法書士業務支援システムを開業と同時に導入されていること。取り扱い内容を特化した場合でも、幅広く案件を受けられる場合でもミスなく正確に仕事をすることは新人だからと関係なく絶対条件です。自信を持って業務をこなし、お客様の満足いく仕事を提供できることが次の仕事にもつながっていきます。
ここからは、司法書士の即独事例についてご紹介します。共通しているのは司法書士業務支援システムを開業と同時に導入されていること。取り扱い内容を特化した場合でも、幅広く案件を受けられる場合でもミスなく正確に仕事をすることは新人だからと関係なく絶対条件です。自信を持って業務をこなし、お客様の満足いく仕事を提供できることが次の仕事にもつながっていきます。
1 二足のわらじ(井手上 刀秀 司法書士事務所)
塾関係のお仕事から司法書士を目指し、試験合格後に地元の鹿児島にUターンされた井手上様。業務の性質上、ミスが許されず経験が少ないことから、早い段階で司法くんの導入を決断されました。 東京での塾の仕事を地元でもやりつつ司業も並行するという、まさに「二足のわらじ」を履いておられますが、司法くんを導入したことによって各種サポートを利用できたり、登記情報の取り込み・作成負荷が減ったりとメリットを実感されているとのことです。→ インタビューはこちら
2 営業経験を活かした(くわはら司法書士事務所)
サラリーマンから未経験で司法書士に独立開業された桒原様。元々、独立志向が強かったことに加え、40歳手前で今後のキャリアを考えた時、お子様に誇れる仕事に就きたいと決意されました。開業時はゼロから顧客を獲得しなければならず苦労をされたとのことです。 司法くんは開業時に導入され、以前利用された時に使いやすかったため選ばれたそうです。不動産の登記情報サービスから正確に情報を取得でき、ソフトの更新速度が早いので、ちょっとしたミスが減ることが業務全体のスピード向上に役立っているとのお言葉をいただいております。→ インタビューはこちら
3 不動産会社での勤務経験を活かした(原 司法書士事務所)
高校卒業後、通信関係の会社に8年、その後に不動産関係企業での9年間の在籍を経て、司法書士試験を受験し即独された原様。 通常業務のかたわら、細切れの時間を使って勉強に励み合格を叶えた原様も、開業後すぐに司法くんの導入をされたとのこと。「システムが使いやすく、費用も安価のためおすすめ」とお褒めのお言葉もいただいております。→ インタビューはこちら