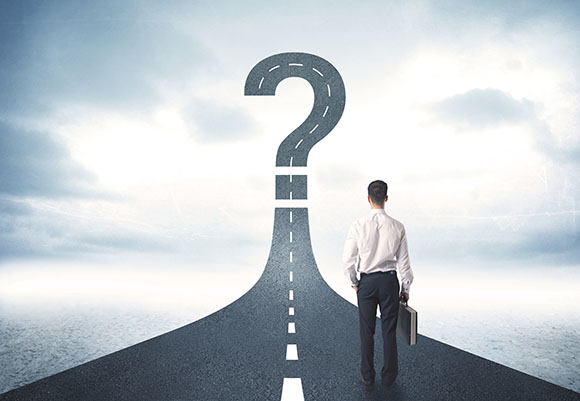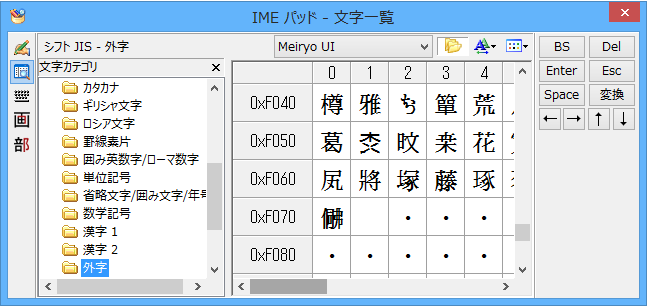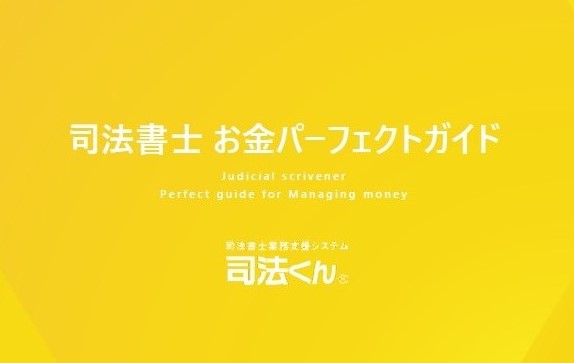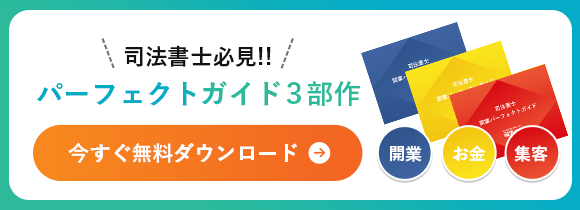SNSを活用する司法書士は少なくありません。
SNSの活用事務所のPRだけでなく、司法書士の知名度を上げたい、司法書士と交流したい、法制度をわかりやすく伝えたいと目的も動機も様々です。このようにSNSは司法書士同士のネットワーキングや情報交換のための有力な手段です。司法書士がSNSを活用する方法にはいくつかのアプローチがあります。
専門知識の発信
司法書士としての専門知識を活かし、SNSを通じて情報を発信することは信頼を築くために有効です。お客様目線でわかりやすく法律を伝えることに注力しましょう。例えば入口として相続登記の義務化など最近の法改正や重要な判例などトレンドに近い話題を解説します。切り口として法律相談の形を取って、よくある法律問題や手続きについてのアドバイスをシェア、代表的なケーススタディを紹介してわかりやすく解説します。登記手続きや相続手続きなど、実際の業務の流れや注意点は完結にポイントをまとめて紹介します。わかりやすい解説だけでなく理解を助けるフローや図解があるとわかりやすいでしょう。
ターゲット層へのアプローチ
SNSを利用して、ターゲットとなる層(相続問題に直面している人々、不動産オーナーや企業など)へアプローチできます。例えば、以下の方法でアピールできます。InstagramやFacebookでは視覚的に訴える投稿をし、手続きや事例を紹介。特にInstagramでは、情報を整理した、インフォグラフィックを利用した分かりやすい画像やショート動画が効果的です。
Xはリアルタイムでの情報発信に向いています。また投稿にスレッドが付くの話題を投稿してシェアやリツイートで気軽に話題が盛り上げることができます。
映像や音声、テロップなどで動画を作りこめるYou Tubeは手間もコストもかかりますが、視聴者にとっては見やすく、わかりやすく編集できれば印象を残すには最適なメディアです。
事例紹介と成功体験のシェア
実際に解決した事例やお客様の声を紹介することで、フォロワーにとって身近で理解しやすい形で司法書士のサービスを知ってもらい、信頼感を高めることができます。匿名でも具体的な問題解決のケーススタディを投稿、お客様の声としてサービスを受けたお客様のリアルな感謝の言葉や成功体験をシェアします。
ライブ配信やQ&Aセッション
SNSでのライブ配信やQ&Aセッションを通じて、フォロワーとの交流を増やすことができます。例えばYou TubeやInstagramでライブ配信をして視聴者からの質問を受け付け、リアルタイムで答えることにより、信頼感を高め、専門性をアピールできます。事前に告知をするとともに、先に質問を募集して回答を用意し、配信時に回答していくスタイルだと準備もできます。
SNS広告の活用
ターゲットを絞った広告を出すことも有効です。例えば、相続や不動産登記の需要がある人々に向けて、Facebook広告やInstagram広告を出すことで、より多くの人々にアプローチできます。
地域や年齢、職業など様々なセグメントで設定ができるので、少額から出稿できます。
コンテンツの定期的な更新
SNSは継続的な情報発信が重要です。定期的に投稿を行い、司法書士としての専門性をアピールし続けることが信頼を築く鍵です。投稿内容もビュー数やいいね数を見るなどして、投稿内容もブラッシュアップしていきましょう。
オンライン相談の提供
SNSを通じて、初回の無料相談やオンライン相談の案内を行うことで、潜在的なクライアントに対してアクセスしやすくします。ZoomやLINEなどのツールを活用して、オンラインでの相談の予約を促進できます。結局はプラットフォームとなるSNSの投稿に信頼があるとよりオンラインでの集客、接客がしやすいでしょう。
司法書士同士の交流とPR
司法書士がSNSやオンラインプラットフォームを利用する目的の一つに、競争相手ではなく仲間として業界を盛り上げるという意義があります。特に、情報共有や自身のブランディングを通じて、司法書士業界全体の発展に寄与しようSNSを活用するのです。例えば遺言書の重要性を啓蒙する活動をSNSで展開し、参加者を巻き込むワークショップなどを実施することで、社会貢献を果たすと同時に、司法書士の認知、業務への信頼感を築くことができます。これにより、新規クライアント獲得への道も開かれ、業務の拡大につながっています。
まとめ
SNSを活用することで、司法書士としての専門性を広く伝え、信頼感を築き、潜在的な顧客にリーチすることが可能になります。コンテンツの質や頻度、ターゲットに合わせた方法を工夫、更新していくことで、効果的にSNSを活用できるでしょう。
SNSは重要なブランディングの一環でもあります。事務所の方針や方向性をSNSでも展開、披露していきましょう。