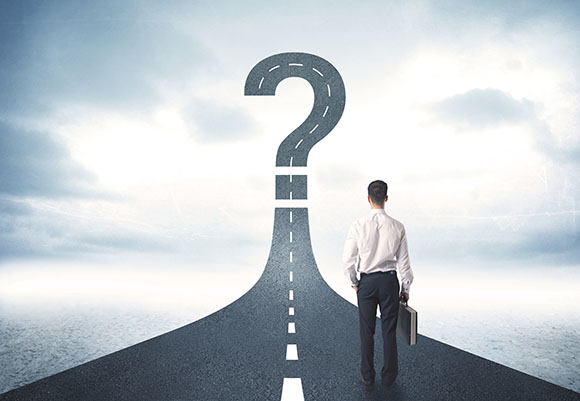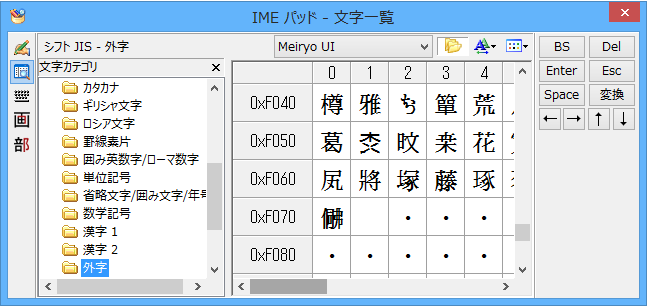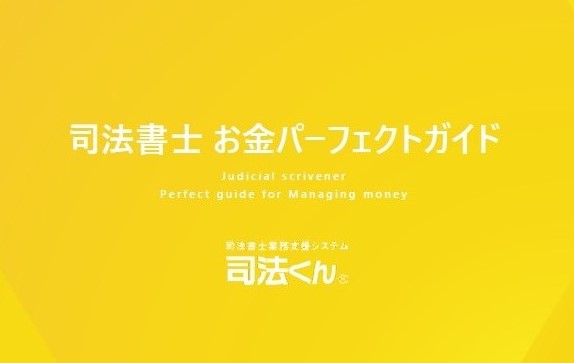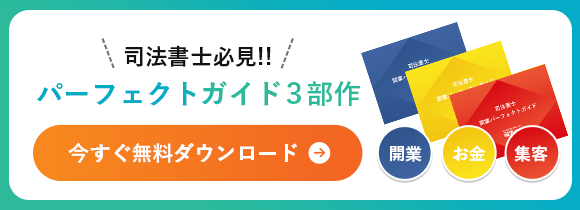1 司法書士とは?
 司法書士は、顧客の依頼を受けた法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成や登記手続、成年後見業務等を主な仕事としています。2020 年 6 月 6 日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第 29 号)が成立し(同月 12 日公布)、その第 1 条において「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する」ことが司法書士の使命とされました。登記を通じて、法的なトラブルを防ぎます。身近な法律問題である金銭消費貸借・不動産売買・不動産貸借等の解決に優れています。ここでは、司法書士に関する基礎情報をご紹介します。
司法書士は、顧客の依頼を受けた法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成や登記手続、成年後見業務等を主な仕事としています。2020 年 6 月 6 日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第 29 号)が成立し(同月 12 日公布)、その第 1 条において「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与する」ことが司法書士の使命とされました。登記を通じて、法的なトラブルを防ぎます。身近な法律問題である金銭消費貸借・不動産売買・不動産貸借等の解決に優れています。ここでは、司法書士に関する基礎情報をご紹介します。
1 給料・年収
「司法書士白書 2020年版」を参考にすると、開業司法書士の平均年収は、男女ともに400~600万円程度です。経営者以外の司法書士は「300〜400 万円未満」が最も回答が多くありました。しかし、司法書士の給与・年収は、勤務・開業にかかわらず、地域や事務所の規模によるため個人差があります。従って、開業司法書士の中には、1,000万円以上の年収の人もいます。2 司法書士のなり方と資格取得の難易度
司法書士になるためには、国家試験である司法書士試験に合格しなければなりません。試験は年齢、学歴を問わず、誰でも受験できます。しかし、試験は高度な専門知識が求められ、法律系の資格の中でも弁護士に次いで難しく、2018年度の合格率はわずか3.5%でした。この難関を突破するためには、大学の法学系学部に進学する、法律の専門学校に通う、司法書士事務所のアシスタントをする、等の対策が必要です。3 雇用の現状と将来性
司法書士は、1993~2001年は年間50名ほどの増加でしたが、最近では毎年300名近い増加、平成31年度は22,632人ととなっています。その影響から、合格しても就職先に困る人や、開業しても競争に苦戦する人が出てきています。また、司法書士の主な仕事である「登記」に対して専門性が下がったことも、厳しい現状の一因です。近年は、インターネット上に登記の申請書のひな型が掲載され、法務局も書き方をサポートしてくれます。従って、司法書士に代理業務を依頼しなくて済むようになりました。これらの要因から、司法書士の将来性は厳しいと予想されるため、新しい事務所形態・提案型業務等の、柔軟な対応を行うことが求められます。4 弁護士との違い
司法書士と弁護士の違いは、「扱える法務業務の範囲」です。司法書士は法律で定められた範囲・分野のみを扱いますが、弁護士は法律業務すべてに対応しています。司法書士は、主に登記・供託を扱う資格です。5 やりがい
司法書士として活躍する上で感じられるやりがいは、2点あります。1つめは、「専門性の高い仕事ができる」点です。難関試験に合格したからこそ、煩雑な法務手続きを扱えるため、誰にでもできる仕事ではないというプライドが持てます。2つめは、「困っている人のサポートができる」点です。問題を抱えた顧客の力になることによって、解決した際に充実感を得られます。平成31年度の統計では会員の年齢層が「41-45歳」の次に「66-70歳」が多いことから定年を気にせず、長く続けられるということも加えていいかもしれません。2 勤務と開業どちらがいいのか?

1 勤務司法書士
勤務司法書士は、「司法書士法人」や「個人事務所」に属した上で、司法書士として活動します。近年は、司法書士法人だけでなく、個人事務所の社会保険加入も増加し、労働環境が整っています。勤務司法書士は、仕事が安定して入ってくる可能性が高いため、「安定志向」の人に向いています。2 開業司法書士
司法書士として開業する際には、最低3年は経験を積むことが推奨されていますが、中には、勤務期間1年未満で独立する人もいます。独立開業に必要なことは、「行動力」です。勤務司法書士と異なり、仕事が常時ある保証はないため、独立には勇気が入ります。しかし、事務所の経営が軌道に乗れば、収入の増加に繋がるため、「上昇志向」の人に向いています。3 年収1,000万や2,000万は本当に可能なのか?
開業司法書士の場合、年収1,000万円や2,000万円を超えることが可能です。開業当初は、一般企業よりも収入が低くなる可能性も小さくありません。徐々に経験を積み、有力なコネクションを増やし、営業力を強化することによって、紹介を広げていくことで高収入を実現できるでしょう。4 実際に司法書士として働く人の本音は?
勤務・開業どちらにもメリットがあります。事務所の方針によって労働環境や所得は大きく左右されます。ここでは、実際に司法書士として働く人の本音をご紹介します。 ・「開業して9年のAさん」 積極的に営業しなければ、年収は500万円を超えることはなく、運転資金や税金を引くと、実際の手取りは月10~30万円程が現状です。ボーナスはなく、平均年収は250万円程度です。独立するメリットは、上司がいないため気を遣う必要がない点です。 ・「大規模法人勤務のBさん」 主な仕事は、大手不動産会社関係の不動産登記手続・相続登記・商業登記です。繁忙期以外は定時退社が当たり前となっており、遅くても19時には退社します。給料やボーナスは、一般の中堅企業と同程度にもらえます。 ・「司法書士歴8年、開業歴5年のCさん」 報酬部分の年収は2,400万円、人件費や賃貸料等の経費が1,200万円かかり、最終的に入ってくる所得は1,200万円です。前職は営業職をしており、司法書士として年収を上げるためには、コミュニケーション能力と経営能力が重要であることを実感しています。3 開業のためにやるべきこと

1 開業費用の平均額
司法書士は、資格と経験さえあれば、必要最低限の備品と場所があれば開業できます。一般的に必要とされる開業費用は50~150万円程度となります。中には、30万円で開業した人もいます。内訳は、プリンターに約2万円、司法書士登録費用に約10万円、事務用品に約8万円、ホームページに約10万円です。自宅で開業し、元々持っている備品を活用することによって、開業資金を最小限に抑えることができます。2 オフィスの構え方と立地を決める
オフィスの構え方として、「自宅」と「テナント」があります。自宅の場合、通勤が不要になることに加えて、テナント料がかかりません。自宅で開業して、軌道に乗ったらテナントに切り替えることも1つの方法です。次に、開業するにあたって、立地は非常に重要です。銀行や不動産会社が集中し、アクセスが便利な「駅前や繁華街」は、営業に有利です。しかし、家賃やテナント料が高額なため、運転資金を多く見積もる必要があります。開業時の予算に合わせて、オフィスの構え方と立地を決めましょう。3 開業に必要なもの
開業に最低限必要なものは、オフィス用品(デスク、イス、来客用テーブル)、通信機器(ビジネスホン)、パソコン、外付けハードディスク、ドットプリンタ、司法書士業務ソフト、文房具です。司法書士は膨大な情報量を扱うため、データを確実に保存できるように、外付けハードディスクは必ず用意しましょう。4 年収を上げるためにできることをやっておく
立地や地域事情を事前に調査し、その土地に特化した開業スタイルを築いておきましょう。例をあげると、競争相手が多い地域では、特定の専門分野に特化する、過疎地域では、幅広い分野の業務を受けられるようにする、等です。また、ハウスメーカーや金融機関、不動産会社とのコネクションを作り、人脈を広げておきましょう。4 廃業するケースもある
 晴れて独立開業した後、廃業となってしまう事務所は少なくありません。ここでは、廃業の原因と、万が一のときの転職先となりうる職種をご紹介します。
晴れて独立開業した後、廃業となってしまう事務所は少なくありません。ここでは、廃業の原因と、万が一のときの転職先となりうる職種をご紹介します。